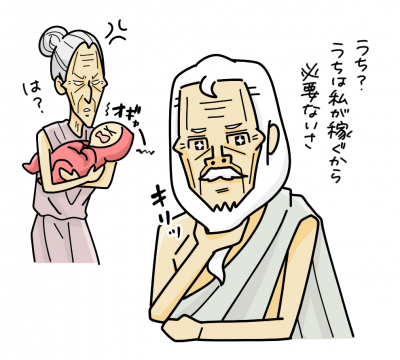
保険は万一の経済的損失に備えてかけるものですが、親だけでなく、子どもにも必要ではないかという意見があります。よく議論になるのが医療費と教育費。特に教育費は、すべて公立の学校に通ったとしても1,000万円レベルでかかると言われているので、具体的に計画を立てて準備すべきでしょう。
子どもを被保険者とした保険で必要なものはなにか、考えてみます。
医療保険
病気や怪我で入院したり、手術を受けたりしたときの経済的負担を減らすために入る医療保険ですが、子どもの入院にはお金がかかるものなのでしょうか? また、子どもは保険で備えた方がいいほど入院する確率が高いのでしょうか?
まず、医療費については、子どもだからといって高くなることはなく、むしろ安くなる傾向があります。各自治体が、子どもにかかる医療費を助成する制度を設けているからです。地域によっては高校卒業までまったくかからないところもあります。
また、子どもには収入がないので、入院することで収入にダメージを与えることはありません。収入がないという点では専業主婦も同じですが、家事ができなくなる穴を家政婦さんなどに頼んで埋めたり、外食が増えたりする可能性があり、子どもと違って支出へ影響を及ぼす恐れがあります。
次に、子どもが入院する確率ですが、厚生労働省が公表している統計を見れば、大人と比べてかなり低いことが分かります。
| 年度 | 平性23年度 | 平性26年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢階級(歳) | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 |
| 総数 | 1,036 | 7,193 | 1,038 | 5,696 |
| 0~4 | 175 | 7,009 | 170 | 6,778 |
| 5~9 | 103 | 4,692 | 92 | 4,422 |
| 10~14 | 98 | 2,916 | 92 | 2,649 |
| 15~19 | 125 | 2,017 | 117 | 1,937 |
| 20~24 | 186 | 2,260 | 165 | 2,240 |
| 25~29 | 254 | 2,708 | 241 | 2,716 |
| 30~34 | 304 | 3,026 | 296 | 3,086 |
| 35~39 | 313 | 3,187 | 304 | 3,280 |
| 40~44 | 347 | 3,397 | 330 | 3,382 |
| 45~49 | 461 | 3,852 | 427 | 3,827 |
| 50~54 | 619 | 4,585 | 591 | 4,664 |
| 55~59 | 854 | 5,421 | 772 | 5,361 |
| 60~64 | 1,135 | 6,786 | 1,064 | 6,514 |
| 65~69 | 1,445 | 8,802 | 1,350 | 8,309 |
| 70~74 | 2,007 | 11,617 | 1,820 | 10,778 |
| 75~79 | 2,927 | 13,363 | 2,635 | 12,397 |
| 80~84 | 4,314 | 13,457 | 3,879 | 12,606 |
| 85~89 | 6,170 | 11,809 | 5,578 | 11,373 |
| 90~ | 9,773 | 9,322 | 8,412 | 9,074 |
※出典:患者調査(厚生労働省)」内「性・年齢別級別にみた受療率」より抜粋
まだまだ不安定な0歳時を除くと、すべての年代で大人より低いですね。一方で外来の受療率は高いですが、今のところ医療保険の主な給付対象は「入院や手術にかかった費用」であり、外来が保障対象になる場合も「入院を伴う外来」としている保険会社がほとんどのため、ここでは特に重要視しないことにします。
以上の理由から、安心を買うという目的以外では、子どもに医療保険はあまり必要ないと言えそうです。
死亡保険
あえて金銭面だけを切り取って述べます。家族が死亡すると葬儀費用が必要ですが、子どもの葬儀費用を保険で用意する必要はないでしょう。子どものために使う予定だった教育資金を葬儀代に回せばいいのです。ドライに考えると、子どもが生きていた方がお金はかかったはずですので、死亡保険を払い込む余裕があるなら、その分を貯蓄するか、養育費全般に回した方が賢明だと思います。
がん保険
小児がんは子どもの死因で上位を占める恐ろしい病気です。発症すると長期間の治療を強いられることが多く、医療費がかさむ恐れがあります。
しかし、小児がんは国が指定する「小児慢性疾患医療費助成制度」を利用できるため、医療費の自己負担額はほとんどありません。
| 階層区分 | 自己負担限度額(月額) | |
|---|---|---|
| 入院 | 外来 | |
| 生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び 永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
| 市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 |
| 前年の所得税が非課税の場合 | 2,200円 | 1,100円 |
| 前年の所得税課税年額が5,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 |
| 前年の所得税課税年額が5,001円~15,000円 | 4,200円 | 2,100円 |
| 前年の所得税課税年額が15,001円~40,000円 | 5,500円 | 2,750円 |
| 前年の所得税課税年額が40,001円~70,000円 | 9,300円 | 4,650円 |
| 前年の所得税課税年額が70,001円以上 | 11,500円 | 5,750円 |
※重症患者に認定された場合は0円
※厚生労働省「小児慢性特定疾患治療研究事業の概要」より抜粋
また、小児がんの発症は1万人に1人ほどの確率と非常に低く、わざわざがん保険に入ってまで備える必要は低いという見方もできます。ただし、専門的な治療になるため遠方の病院で手術したり、長期入院したりすることで、親の宿泊費やお見舞いのための交通費がかかる可能性はあります。医療費以外の出費に備えるという意味では、保険が役立つこともあるでしょう。
こども(学資)保険
冒頭でふれたとおり、教育資金は必ず必要になる大きな負担なので、妊娠したらすぐに対策を練るくらいの周到さが必要です。こども(学資)保険か、積立の定期預金などで備えるかは、貯蓄性の高さ、税制面の優遇、契約者(親)が死亡したときの万一の資金確保などを考慮に入れると、こども保険の方が有利な場面が出てきます。特に、契約者が死亡または高度障害状態になったときに適用される「以降の保険料免除」という仕組みは、銀行はもちろん他の金融商品にはないメリットです。
貯蓄目的にこども保険を選ぶのですから、医療保障を特約で付ける「保 障型」と呼ばれる保険は避けた方がいいでしょう。保険料のいくらかが医療保障に充てられるため、返戻率(貯蓄率)が100%を割ってしまう、元本割れ状態が起こります。そもそも、医療保障の必要性が低いことは先ほど確認したとおりです。
なお、こども保険の代わりに、生命保険の『低解約返戻金型』の保険で備える手もあります。一般的な生命保険より保険料が安く、こども保険と同等かそれ以上の貯蓄率もあり、契約者に万一のことが起こった際はすぐに死亡保険金を受け取れるという商品です。
※詳細は、用語集「低解約返戻金型保険」で解説しています。
個人賠償責任保険
好奇心旺盛で注意力散漫な子どもがしでかすトラブルのなかで、最も怖いのが他人の身体や物を傷つける行為です。故意でないにしろ、相手に多大な損害を与えてしまった場合、親はその損害を補償する法律上の義務を負うことになります。
ここ最近で顕著な例としては、子どもが運転する自転車がお年寄りや身体の弱い人を跳ね、死亡させたり寝たきり状態にさせたりした結果、数千万円の支払い命令が出ています。そんな大金、自分で用意できる人は一握りでしょうから、まさに保険の出番でしょう。
個人賠償責任保険は、他の保険の特約で付帯するのが一般的です。こども保険のほか、火災保険や自動車保険、またクレジットカードの特典としても付いています。月額100~200円程度で1億円レベルの損害をカバーできる保険なので、子どもに限らず、大人も入っておきたいコストパフォーマンスの高い補償です。
※詳細は、用語集「個人賠償責任保険」で解説しています。
まとめ
以上をまとめ、必要度の高さを評価付けしてみました。参考になれば幸いです。
| 保険の種類 | 必要度の高さ | 備考 |
|---|---|---|
| 医療保険 | ★★☆ | 子どもの医療費は助成制度等で負担を軽減できることが多い |
| 死亡保険 | ★ | 使うはずだった教育費で補てんすればいい |
| がん保険 | ★★ | がんの治療費は公費でほぼ負担される |
| こども保険 | ★★★☆ | 貯蓄性が高く確実性がある。ただし途中解約すると大損してしまう。 他の金融商品で代替できないこともない |
| 個人賠償責任保険 | ★★★★★ | 保険料が安く補償対象範囲が広い |

